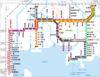| ******************************************************************* |
| 広島市内を走る路面電車。通称「広電」。 |
| ここではその「広電」の駅にちなんだショートストーリーを公開しています。 |
| 全て作り話の”つもり”ですが、広電に乗ればそんな風景も・・・ |
| ******************************************************************* |
広電物語 : 「宇品三丁目のスーパーサブ」
「アキヒロ、ちゃんと携帯の充電器も持ったの?」
「持ったよ、うっせーな。じゃあ行ってくるからな」
「がんばるのよ。お母さんも応援に行くからね!」
「来なくていーよ。ミサキ来るし。お前はハルヒロでも探してろって」
「ハルヒロのことはいいの!お母さんがどうにかするから!怪我には気をつけるんだよ」
「うっせーな、サッカーやってんだから怪我くらいするだろ。じゃあな、行ってくるからな」
「がんばるんだよ」
あんたにはヒロトと同じ血が流れてんだから、と言おうとしてぐっと堪えた。
ベランダから息子の後を追う。
息子は宇品三丁目の電停に向かってスタスタと後ろも振り返らず行ってしまった。
まったく男の子ってのはそんなもんね。
息子のアキヒロは宇品三丁目から五駅ほど離れた場所にある高校に通っている。
いつもなら自転車で出かけていくのだが、今日は学校で一旦集合してそこからバスで移動だ。
予定では一ヶ月ほど帰ってこない。
いや、予定じゃないな、希望では、だ。
毎年一月はサッカーをやっている高校生にとって特別な月だ。
全国高校サッカー選手権の全国大会があるから。
息子がそこに出ることになるまでは知りもしなかった。
ただただグレもせず日に焼けて帰ってくる息子を見て安心し、膝から血を流しながら帰ってくる息子を見て不安に思った。
ある日アキヒロが、「おい、おれ今日勝ったら正月は墓参り、行けないから」と言い出した。
「何言ってるの!」と怒鳴ったら、一ヶ月ぶりに家に帰ってきた旦那が三ヶ月ぶりに口を聞いた。
「おい。アキヒロは全国大会に出るんじゃ。行かせてやれや」
さすが長距離トラック運転手、迫力が違う。
声に詰まった。
自慢じゃないがサッカーは全くわからない。
ロクに働かない、いや、働いてもロクに稼ぎを持って帰らない旦那のせいで、いつも土日もパートに出ているから母親会というのにも最初しか行ったことがない。
みんな頑張って炊き出しとかしてるのにアキヒロ君のお母さんは、なんて言われてるに決まってる。
説明をしないアキヒロに変わって他の家の母親が説明をしてくれた。
どうやらアキヒロは高校サッカーの全国大会のために東京に行くらしい。
それはすごいことなんだそうだ。
アキヒロは「スーパーサブ」っていう八百屋みたいな名前のポジションらしい。
そこで活躍すればプロのスカウトの目にも留まるかもよ、とそのお母さんは言っていた。
どうせ旦那だって大して分かっていないんだ。
よくわからないが、「全国大会」という響きが誇らしげなだけだ。
トラック仲間で応援に行くから、と言っていたがアキヒロがそれとなく断っていた。
飲み屋のオネーチャンと運転手がゾロゾロと行くような場所ではないと思う。
ミサキとかいう彼女が来る前で、これが父親だよ、なんて紹介できるような風体で表れるとは思えないし。
幸いなことに私はパートも休めたし、その母親がアキヒロ君のお母さんも一緒に、と言ってくれた。
もっとも、何回話しても「アキヒロ君のお母さん」と彼女が言うのは、私の名前を知らない上に、母子家庭で苗字を呼ぶのははばかられる、という配慮からに違いなかった。

唯一の心配はハルヒロのことだ。
おばぁちゃん、つまり旦那の母が泣くってから半年、家を出たきり帰ってこない。
まだ高校一年生だ。
出てから二週間は心配で心配でならなかった。
二週間目くらいに電話が携帯からかかってきた。
「探すなよ。別に生きとるけぇ」
とだけハルヒロは言って電話を切った。
わんわん泣いた私に旦那が冷たく「うるせぇ」と言った。
「心配じゃないんねぇ!」とこの時ばかりはさすがに怒鳴った。
「おれが家を出たのは中学生じゃ。でもこうやって生きとる」
と旦那が凄んだ。
あんたみたいになるじゃないね!と言い返すことなんてとてもできない。
そのうち時間が経つにつれて、心配は相変わらず消えないものの、自分の中で消化もできた。
たまにハルヒロはアキヒロにメールなんかもしているようで。
「おれも大阪に行ってみたいのぉ」なんてアキヒロが言っている。
兄弟なんて、家族なんて色んな形があるんだ。
そんな時私はいつもマミとヒロトのことを思い出す。
私は父親と母親の間に生まれた初めての女の子であり、父親にとっては二人目の女の子だった。
マミは義理の姉だ。父親と飲み屋の娘との間にできた、所謂私生児だった。
飲み屋の娘が何かの容疑でパクられたときに、不憫に思った母親が引き取った。
父親に黙って、店まで引き取りに行ったのだそうだ。
当時我が家にはまだ一歳の私と二人の兄がいた。
つまり私には急に二つ年上の姉が出現したことになる。
父親はなんとなく後ろめたそうな素振りを見せてはいたような気がするが、母親は貰い子としてマミを普通に育てていたような気がする。
「普通に」というのは他の兄弟と同列に、という意味ではない。
時代背景的に、広島には親のいない子が当時はそこかしこにいた。
彼らの多くは親族によって引き取られ、育てられていたが、その子たちと同じようには、という意味だ。
ただ、うちは経済的には恵まれていたので食べ物が十分にあった分、むしろ幸福な生活だったかもしれない。
ところがマミは十六歳のときに妊娠して家を出てしまった。
携帯電話もなかった時代、私達の「半分のつながり」は忽然と消えて無くなってしまった。
マミの子がヒロトだと言うことを知ったのは、それから随分経ってからだ。
すっかり大きくなったヒロトは有名なサッカー選手になっていた。
これまた全然詳しくないのでわからないが、日本代表のエースだ、とアキヒロが言っていた。
アキヒロはヒロトが親族であることを知らない。
私だって、テレビでそれを見ただけだ。
ヒロトの特集をやっていてドキュメンタリーで。
興味もなくチャンネルを弄くっていたところに、マミそっくりの男の子が急に画面に出てきたのでびっくりした。
それは幼い頃のヒロトの写真だった。
私にはすぐにわかった。
ヒロトは決して自分の素性を話さなかった。
どこまで彼が知っているのかも、わからない。
私はその事実をグッと胸の奥に飲み込んだ。
誰にも喋ったことはない。
ベランダに数分もいると、年が明けて間もない冬の朝の冷気が身体を強ばらせる。
それでも私はアキヒロが忘れ物を取りに来るような気がして、ハルヒロが帰ってくるような気がしてなかなか部屋に戻ることができない。
旦那も正月から戻ってこないが、まぁそれはどうでもいい。
アキヒロにだって、ハルヒロにだって、日本代表のエースと同じ血が流れているんだ。
エースとスーパーサブでは、なんかすごい違いがある気がする。
いや、待てよ。私にだって同じ血が流れているはずなんだが。
さすがに風邪を引きそうだったので急いで部屋に戻って、ストーブのまで手足の感覚をゆっくりと元に戻していく。
なぜか私は、アキヒロの試合を、ハルヒロも観に来るような気がした。
(この物語はフィクションです)